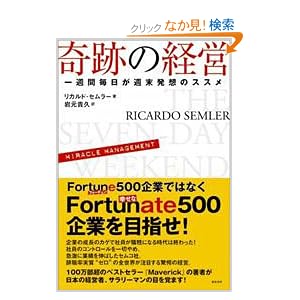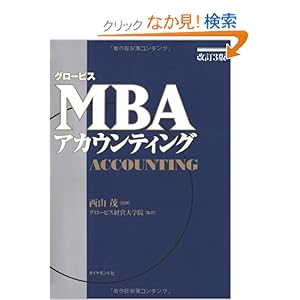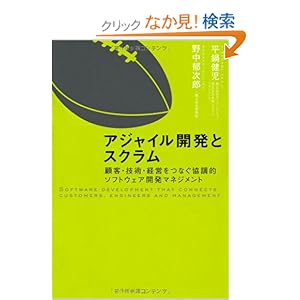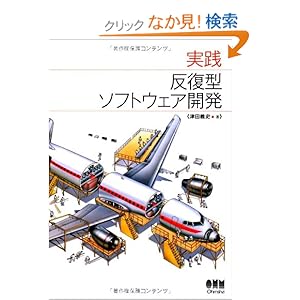偶然、「ビブリオバトル」(文芸新書)を読んで面白そうでしたので、やってみました。すごく面白かったです。「人を通して本を知る、本を通して人を知る」というのはこういう事かと実感出来ました。
ところが、課題もありました。次回やる事があればこれらを改善した形で行いたいと思います。
・そもそもこの内容では初めての人が来にくい
→今回1人だけ来てくれましたが、他は常連ばかりでした。
・質問タイムはその気になれば何時間でも出来る
→そもそも技術が好きな人の集まりでしたので語る語る・・(笑)
・同票になった時のルールがない
→今回2冊が同票になり、決選投票でも同票になりました
・違うジャンルの本を較べられない
→今回、技術書とマネージメントの2種類が出ました
・電子書籍で読んだ人が紹介しにくい
→一人はわざわざ買って持ってきてくれました
事前に申告して下さった方は5名だったのですが、急に阪井さんと小川さんが発表して下さる事になり、7冊になりました。フラッシュの電子あみだくじ(笑)で順番を決めました。
http://mwsoft.jp/programming/webtools/random_chooser_amida.html
急にお願いしたお二人はみごとに最後にまわりました。電子あみだくじやるな~。
5分を計測するタイマーもフラッシュの物にしました。
http://scienthrough.qee.jp/biblio/bibliotimer.html
両ソフトの作者のかた、ありがとうございました。それでは始まりはじまり
ITプロジェクトは失敗し、納期が遅れるのが当然というイメージがあります。この本はプロジェクトが遅れないための簡単で画期的な方法を提示しています。それに登場人物数名の問題意識、課題がストリー形式で説明され解決されるので面白いです。
あるタスクが90%の確率で終わるのが外部スケジュールで、50%の確率が内部スケジュールです。その差がバッファになりスケジュールの最後に置きます。
これを読むたびにクリティカルチェイン・プロジェクトマネージメント手法の創造に立ちあう事が出来ます。
![]()
電子BOOKで読んだのですが、今回紙の本を買いました。通勤で読むにはがっつりしています。設計作業と実装作業を結びつける方法が書かれたものです。
プログラムの自動生成には限界があります。この本では、仕様(設計情報)を記述することで生成的(ジェネレーティブ)にコードを作り出そうという理論と実践が記述されています。渡辺さんのXEAD DRIVERはまさしくこれだと思います。
ITの歴史に必ず残る本です。
ドラッガー本です。プロフェッショナルの条件が爆発的に売れた中で発売された4冊目。あまり注目されませんでした。資本主義が「ブルジョアジーと労働者の対立」という視点から、社会主義が出てきましたが、産業革命で圧倒的に生産性が高まり社会主義の必要性がなくなりました。この本は、Management of Technology(MOT)という視点でテクノロジー(技術)が文明に果たしてきた役割が歴史的に書かれています。
皆さん管理される事は好きですか?これはブラジルで大成功した経営者の驚くべき経営手法を説明したものです。まず、コントロールはいらない。コントロールするという事は人を信用しないという事だからです。それに方針や戦略もいらない。大人だからみんな、自分がやる事わかっているよねという事です。さぼる人が出てきてもいい。クビにすると他の人が疑心暗鬼になるからです。
ある意味アジャイルの組織論とも通じる方法論だと思います。
システム設計には会計の知識が必要だと今までも言ってました。簿記の試験は何の役にも立ちません。経営的な視点がないからです。この本は貸借対照表や損益計算書を経営的な視点で学ぶ事が出来る本です。今まで改定3版まで出ていてすべて持っています。それは法律が変わっても専門書を読む時間がないためこの本をベースに勉強しているためです。最新の3版では2006年の会社法改正や内部統制が追記されています。
これを読むと、経営者と会話する知識を得る事が出来ます。
Aster、昔のJUDEというツールを作る会社の平鍋さんと、スクラムを作った野中先生の対談集です。帯に「日本生まれ米国育ちのスクラム」と書いてありますが、それが嘘である事が本に書かれています。野中先生は、トヨタ方式を拡張した生産の手法について実績値を入れた論文を書いていました。サザーランドがアジャイルをすすめていてうまくいかず、野中先生の論文をみつけて進めた方法論なのです。
そういう歴史的な事が詳しく書かれた本です。
マイクロソフトの技術者が書かれた本です。開発プロセスを支援するツールについて具体的に書かれています。ソース管理(SCM)、ビルド管理(CI)、障害管理(BTS)という三種の神器について詳しく説明されています。例えば、複数のソースをマージするとサブバージョンでトラブルことが良くありますが、実はマージにはいくつかの種類があり、どれをどういう時に使うかが良く理解出来ます。
実践でやっていた事を体系的に整理させてくれた本です。
------------------------------------
さて、皆さんはどの本が「一番読んでみたい」と思われましたか?ここで1人1票の投票をしたのですが、すぐには決まらないということで5分間休憩しました。
推薦図書のタイトルを良く見ると、技術書と経営書にまっぷたつに分かれています。その分野の違う本をどちらが選ぶのは難しいという声が多くあがりました。「それぞれの中なら選べるけど」という声でした。そういえば、このビブリオバトルが生まれたのは京大の研究室でどの本で研究するのが良いかを決めるのに持ち合ったことだと本に書いてありました。この勉強宴会はまだ方向性が決まっているので良いのですが、ノンジャンルのビブリオバトルは面白くないと感じました。次回やるとしても来年ですが、次はもう少し範囲を絞ってやりたいと思います。
また、最後の反復型ソフトウェア開発という言葉について少し議論がありました。オープンソースやパッケージの開発のように、ずっと開発が続くソフトウェアについてのツールの話なら理解しやすいと思います。ところが業務向けのソフトウェアも実はこまめにバージョンアップを繰り返し「変化をみこす」必要があるのです。プロジェクトの定義が「目標と期限がある業務」であれば、ソフトウェア開発はプロジェクトではないのかも知れないという発言までありました。
今回発表していただいた本は、どれも1冊あたり2時間・3時間語っても時間が足りないほど面白く示唆に富み勉強になるものばかりです。特に読んだ事のある人は「質問」と手を挙げながら質問でなく自分なりの書評を述べ出すという面白さ。
1冊10分発表20分質疑くらいで、事前にちゃんとプレゼン資料を作って本のエッセンスを説明し議論するという方式でもこの勉強宴会なら充分に成り立つと思いました。
さて、投票です、タカタカタカタカタカ・・・・
------------------------------------
投票になりました。一冊ずつ手を挙げてもらうと、次の2タイトルが同点になりました。
・ テクノロジストの条件
・ MBAアカウンティング
ビブリオバトルの公式ルールでも同点の時にどうするかのルールがありません。しかたないのでこの2つに絞って決選投票したところ・・・・またしても同点(笑)
この2つを2013年度関西IT宴会 チャンプ本と決めました。
参加して頂いたみなさま、ありがとうございました
ところが、課題もありました。次回やる事があればこれらを改善した形で行いたいと思います。
・そもそもこの内容では初めての人が来にくい
→今回1人だけ来てくれましたが、他は常連ばかりでした。
・質問タイムはその気になれば何時間でも出来る
→そもそも技術が好きな人の集まりでしたので語る語る・・(笑)
・同票になった時のルールがない
→今回2冊が同票になり、決選投票でも同票になりました
・違うジャンルの本を較べられない
→今回、技術書とマネージメントの2種類が出ました
・電子書籍で読んだ人が紹介しにくい
→一人はわざわざ買って持ってきてくれました
事前に申告して下さった方は5名だったのですが、急に阪井さんと小川さんが発表して下さる事になり、7冊になりました。フラッシュの電子あみだくじ(笑)で順番を決めました。
http://mwsoft.jp/programming/webtools/random_chooser_amida.html
急にお願いしたお二人はみごとに最後にまわりました。電子あみだくじやるな~。
5分を計測するタイマーもフラッシュの物にしました。
http://scienthrough.qee.jp/biblio/bibliotimer.html
両ソフトの作者のかた、ありがとうございました。それでは始まりはじまり
<山本さん>
クリティカルチェーン―なぜ、プロジェクトは予定どおりに進まないのか?ITプロジェクトは失敗し、納期が遅れるのが当然というイメージがあります。この本はプロジェクトが遅れないための簡単で画期的な方法を提示しています。それに登場人物数名の問題意識、課題がストリー形式で説明され解決されるので面白いです。
あるタスクが90%の確率で終わるのが外部スケジュールで、50%の確率が内部スケジュールです。その差がバッファになりスケジュールの最後に置きます。
これを読むたびにクリティカルチェイン・プロジェクトマネージメント手法の創造に立ちあう事が出来ます。
<久保さん>
ジェネレーティブ・プログラミング
電子BOOKで読んだのですが、今回紙の本を買いました。通勤で読むにはがっつりしています。設計作業と実装作業を結びつける方法が書かれたものです。
プログラムの自動生成には限界があります。この本では、仕様(設計情報)を記述することで生成的(ジェネレーティブ)にコードを作り出そうという理論と実践が記述されています。渡辺さんのXEAD DRIVERはまさしくこれだと思います。
ITの歴史に必ず残る本です。
<野村さん>
テクノロジストの条件ドラッガー本です。プロフェッショナルの条件が爆発的に売れた中で発売された4冊目。あまり注目されませんでした。資本主義が「ブルジョアジーと労働者の対立」という視点から、社会主義が出てきましたが、産業革命で圧倒的に生産性が高まり社会主義の必要性がなくなりました。この本は、Management of Technology(MOT)という視点でテクノロジー(技術)が文明に果たしてきた役割が歴史的に書かれています。
<杉本さん>
奇跡の経営皆さん管理される事は好きですか?これはブラジルで大成功した経営者の驚くべき経営手法を説明したものです。まず、コントロールはいらない。コントロールするという事は人を信用しないという事だからです。それに方針や戦略もいらない。大人だからみんな、自分がやる事わかっているよねという事です。さぼる人が出てきてもいい。クビにすると他の人が疑心暗鬼になるからです。
ある意味アジャイルの組織論とも通じる方法論だと思います。
<佐野>
MBAアカウンティングシステム設計には会計の知識が必要だと今までも言ってました。簿記の試験は何の役にも立ちません。経営的な視点がないからです。この本は貸借対照表や損益計算書を経営的な視点で学ぶ事が出来る本です。今まで改定3版まで出ていてすべて持っています。それは法律が変わっても専門書を読む時間がないためこの本をベースに勉強しているためです。最新の3版では2006年の会社法改正や内部統制が追記されています。
これを読むと、経営者と会話する知識を得る事が出来ます。
<阪井さん>
アジャイル開発とスクラム 顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメントAster、昔のJUDEというツールを作る会社の平鍋さんと、スクラムを作った野中先生の対談集です。帯に「日本生まれ米国育ちのスクラム」と書いてありますが、それが嘘である事が本に書かれています。野中先生は、トヨタ方式を拡張した生産の手法について実績値を入れた論文を書いていました。サザーランドがアジャイルをすすめていてうまくいかず、野中先生の論文をみつけて進めた方法論なのです。
そういう歴史的な事が詳しく書かれた本です。
<小川さん>
反復型ソフトウェア開発マイクロソフトの技術者が書かれた本です。開発プロセスを支援するツールについて具体的に書かれています。ソース管理(SCM)、ビルド管理(CI)、障害管理(BTS)という三種の神器について詳しく説明されています。例えば、複数のソースをマージするとサブバージョンでトラブルことが良くありますが、実はマージにはいくつかの種類があり、どれをどういう時に使うかが良く理解出来ます。
実践でやっていた事を体系的に整理させてくれた本です。
------------------------------------
さて、皆さんはどの本が「一番読んでみたい」と思われましたか?ここで1人1票の投票をしたのですが、すぐには決まらないということで5分間休憩しました。
推薦図書のタイトルを良く見ると、技術書と経営書にまっぷたつに分かれています。その分野の違う本をどちらが選ぶのは難しいという声が多くあがりました。「それぞれの中なら選べるけど」という声でした。そういえば、このビブリオバトルが生まれたのは京大の研究室でどの本で研究するのが良いかを決めるのに持ち合ったことだと本に書いてありました。この勉強宴会はまだ方向性が決まっているので良いのですが、ノンジャンルのビブリオバトルは面白くないと感じました。次回やるとしても来年ですが、次はもう少し範囲を絞ってやりたいと思います。
また、最後の反復型ソフトウェア開発という言葉について少し議論がありました。オープンソースやパッケージの開発のように、ずっと開発が続くソフトウェアについてのツールの話なら理解しやすいと思います。ところが業務向けのソフトウェアも実はこまめにバージョンアップを繰り返し「変化をみこす」必要があるのです。プロジェクトの定義が「目標と期限がある業務」であれば、ソフトウェア開発はプロジェクトではないのかも知れないという発言までありました。
今回発表していただいた本は、どれも1冊あたり2時間・3時間語っても時間が足りないほど面白く示唆に富み勉強になるものばかりです。特に読んだ事のある人は「質問」と手を挙げながら質問でなく自分なりの書評を述べ出すという面白さ。
1冊10分発表20分質疑くらいで、事前にちゃんとプレゼン資料を作って本のエッセンスを説明し議論するという方式でもこの勉強宴会なら充分に成り立つと思いました。
さて、投票です、タカタカタカタカタカ・・・・
------------------------------------
投票になりました。一冊ずつ手を挙げてもらうと、次の2タイトルが同点になりました。
・ テクノロジストの条件
・ MBAアカウンティング
ビブリオバトルの公式ルールでも同点の時にどうするかのルールがありません。しかたないのでこの2つに絞って決選投票したところ・・・・またしても同点(笑)
この2つを2013年度関西IT宴会 チャンプ本と決めました。
参加して頂いたみなさま、ありがとうございました